相続人には年齢制限がないため、未成年者や胎児が相続人となることもあります。
遺産分割協議には全ての相続人が参加し、話し合う必要があるものの、未成年者や胎児の場合はどのように対応すればよいのかわからず、お困りの方もおられるのではないでしょうか。
今回は、未成年者や胎児が相続人となるケースで重要となる「特別代理人」について詳しく解説します。
未成年者に特別代理人が必要なわけ
相続が開始したら、全ての相続人が参加して遺産分割協議を行うことになりますが、未成年者が相続人となる場合は、本人が法律行為を行うことができないため、法定代理人の同意を得る必要性が出てきます。
ところが、相続においては、子の法定代理人である親も同じく相続人であるケースが多く、互いに利害が対立する関係となってしまいます。
そのため、遺産分割において親は子の法定代理人になることができず、代わりに「特別代理人」を選任して未成年者の相続手続きを助けることになるのです。
親が法定代理人となれるケースとなれないケース
相続人が誰になるのかによって、親が子の法定代理人になれる場合とそうでない場合に分かれます。
具体例を見ていきましょう。
親が相続人ではなく子だけが相続人であるケース
離婚しているため母親は相続人にはならないが、子は相続人となる場合については、母親と子の間で利益が相反しないため、母親が未成年者である子の代理人となることができます。
親も子も相続人であるケース
両親が婚姻中に(例えば)父親が亡くなり、母親も子も相続人となるケースについては、母親と子の間で利益相反関係になるため、母親は子の法定代理人として遺産分割協議をすることはできず、別途特別代理人を選任しなければなりません。
利益相反関係とは、「相続人同士の利害が対立する」状態であり、いくら母親であっても遺産分割協議としては子に対してフェアではありません。
そのため民法では、子の利益を守るために母親は法定代理人として子の遺産分割協議に参加することはできないとしています。
法定代理人は、相続人ではない信頼できる親類に依頼するか、あるいは弁護士に依頼して特別代理人になってもらうケースが一般的です。
家庭裁判所に対して特別代理人の申し立てを行い、認められれば候補者の中から特別代理人が選任されます。
そして、特別代理人になった者は、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
親が相続放棄すれば特別代理人は不要
親と子の両者が相続人となる場合でも、親が相続放棄をすれば相続人ではなくなるため、特別代理人の選任は不要になります。
また、親と子両者が相続放棄する場合についても同様です。
例えば、相続財産が債務超過の場合で、親が相続放棄をするのであれば、子も特別代理人の選任なく、相続放棄ができます。
特別代理人が必要なのは、あくまで親と子の両者が相続人となる場合なので覚えておきましょう。
特別代理人がいれば胎児は相続することができるのか
まだ出生していない胎児を相続人とするかどうかは、民法に規定があります。
- 胎児であってもすでに生まれた者として相続人になる。
- 死産した場合は相続人とはなれない。
つまり、相続において胎児は生きて産まれてくるかどうかがポイントとなります。
胎児の状態で遺産分割協議を開始し話をまとめても、万が一死産してしまった場合は胎児の存在抜きで遺産分割協議をやり直す必要が出てくるのです。
ですから、胎児の出生を待ってから、遺産分割協議を開始する必要があります。
また、胎児の場合も未成年者となりますので、親が相続人である場合は別途特別代理人を選任しなければなりません。
その際の条件や手続きは、未成年者の場合と同様です。
子どもの相続に関する繊細な相談は相続に思い入れの強い当事務所まで
大人は自分で自分の法律行為ができますが、未成年者は胎児も含めて法律行為ができません。
本来なら親が代理人となるのですが、親も相続人で子との利害が相反する場合は、特別代理人が必要になるなど、手続きが複雑化します。
特別代理人の選任が必要になるケースは、通常の相続とは違い、特別代理人選任申立てなど、やらなければならないことが増えますので、早い段階で当事務所にご相談いただくことをおすすめします。
相続の問題は、法的な解釈のみで解決できるわけではありません。
相続人の皆様が今どのような状態にあるのか把握した上で、適切で納得のいく解決を目指します。
まずはお気軽にご相談ください。

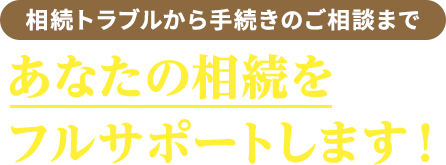
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。