相続財産の対象は借金等の債務も含まれます。
それを相続したくない場合は、「相続放棄」という手続きによって相続自体を放棄することができます。
ただし、限られた期間内に手続きが必要であり、税務面への影響も危惧されるため注意が必要です。
ここでは、相続放棄の手続き概要と、税理士登録のある当事務所の弁護士によるサポートについて解説します。
相続放棄は相続人を守るための選択肢
故人の財産構成によっては、金銭的価値のあるプラスの財産よりも借金等を含むマイナスの財産の方が多く残されていることもあります。
この場合、そのまま相続してしまうと生活が困窮してしまう可能性もあるでしょう。
この場合「相続放棄」という手続きをとることで、相続内容によっては一切の相続財産を放棄することが可能です。
相続放棄の流れとお金にまつわる注意点
相続放棄を検討している場合、やらなければならないのが遺産の一覧を作成し、全体的な損益を明らかにすることです。
相続財産の調査を行い、その上で相続放棄の手続きを行うことになります。
遺産の全体像を把握するための財産調査を行う
マイナスの財産よりプラスの財産の方が多ければ、相続放棄を行う必要がありませんので、まずは丁寧に被相続人の財産調査を行う必要があります。
プラスの財産調査
預貯金:被相続人の通帳や取引明細を見ながら確認していきます。
昨今では銀行の取引メッセージをメールで受け取る仕組みもありますので、被相続人のメールの確認も忘れず行います。
不動産:自宅に不動産関連書類があることがわかっている場合を除き、他にも土地建物の所有が想定される場合は役所で名寄帳を調べます。
固定資産税の納税通知書や領収証が残っている場合もありますので、注意深く探しましょう。
マイナス財産の調査
気をつけたいのが借金等のマイナス財産の存在です。
被相続人の身の回りを探して、契約書や請求書、返済明細等をよく探すことが大切です。
自宅で見つからない債務に関しては、債権者から電話連絡によって発覚することもあります。
また、通帳記帳をして毎月引き落とされている金額があれば、何らかの債務を返済している可能性がありますので、引き落とし先や振込先に連絡して確認しましょう。
相続放棄書類の作成と提出
家庭裁判所に対する相続放棄書類の提出は、申述といいます。
財産の全容を把握した上で相続放棄の意思を決定したら、相続開始から原則3ヶ月以内に放棄の申述を行わなければなりません。
申述には次の書類を用意し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
- 相続放棄の申述書(家庭裁判所かホームページから入手)
- 戸籍の附票(被相続人の戸籍の附票か住民票の除票)
- 申述を行う相続人の戸籍謄本
- 収入印紙800円分と家庭裁判所が指定する切手
ほか、相続人が親族内のどの立場にあるかにより、添付書類は変わってきますので、事前に裁判所に確認することが大切です。
相続放棄をすると相続権が次順位の相続人へ移行
相続放棄後の相続権については消滅するわけではなく次順位の相続人に移行します。
例えば、被相続人の子が全員相続放棄をすると、相続権は第二順位である直系尊属の親に移行するのです。
直系尊属がすでに亡くなっていたり、相続放棄をしたりした場合は、最終的に被相続人の兄弟姉妹にまで相続権が移行するので、債務超過を理由に相続放棄をする際には、事前に次順位の相続人にも相続放棄する旨を伝えておくのが親切です。
税理士登録のある弁護士がお力になります。
当事務所では、遺言書の作成を希望されるご依頼者様の意思を最大限尊重するよう心がけています。
残された相続人を納得させる形で遺言書を作成するにはどうすれば良いのか、自分1人ではわからないことも相続に強い弁護士がサポートしますので安心です。
相続放棄は、行う方は全てを放棄すれば良いだけですが、残された相続人が大変な思いをすることも考えられます。
放棄の手続き自体は簡素であるものの、相続にまつわる一連の手続きは非常に複雑で、財産や負債をどう把握し処理すべきか整理することも大きな課題です。
実際、相続全般に関しては、法的問題や金銭の専門的知識など、わからないことが多すぎるといえます。
最終的に相続税の納税まで辿り着くには、どうしても専門家のサポートが欠かせません。
ご依頼者様の気持ちがわかる弁護士
当事務所では、弁護士自身が相続問題で困難を経験していることから、ご依頼者様の気持ちに寄り添いながら専門家としてのサポートをご提供することができます。
税理士登録もあるため、税務面において専門的見地に基づく遺言書を作成したり、適切な相続放棄のサポートを行ったりすることが可能です。
法律の世界は一概に解釈のみでうまくいくものではありません。
公式に当てはめて終わりではなく、ご依頼者様にとってのベストな解決策をともに探り、できるだけ満足あるいは納得のいく解決を目指していきたいと考えています。
相続に関するご不安やお悩み事がある方は、お気軽にご相談ください。

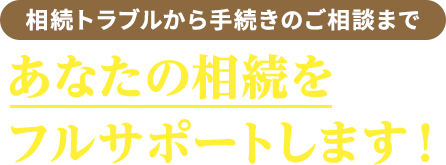
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。