平成30年7月に、約40年ぶりとなる相続法の見直しが行われました。
これまでの相続法と何が変わったのか、ここでは法改正による変更点や重要なポイント等を説明していきます。
大規模な相続法の見直し
近年、日本は高齢化社会から高齢社会へと向かっており、相続の取り扱いについても見直しの必要性が出てきました。
相続において、被相続人だけではなくその配偶者も高齢化していることから、残された配偶者の生活を守るための環境整備が求められてきたのです。
そして平成30年7月に大規模な相続法の見直しが行われました。
このような法改正による変更点を理解し活かすためには、やはり専門的な知識と経験が欠かせません。
当事務所では、法的な回答を示すことはもちろん、ご依頼者様が争いを抱えている場合はこれを把握した上で最善と思われる解決策を提示しています。
相続の問題は一概に法的解釈のみではうまく行かず、公式にあてはめて終わりという世界ではありません。
あくまでもご依頼者様と共に最適解を探り、できるだけ満足あるいは納得のいく解決に導けるよう目指しています。
配偶者の生活を守る「配偶者居住権」
故人名義の建物に住んでいた場合、配偶者は相続開始後も一定期間もしくは終身に渡り、無償でその建物に住み続けることができる権利を持てるようになりました。
改正法では、建物に関する権利を次のように分離します。
| 配偶者 | 配偶者居住権 |
|---|---|
| 配偶者以外の相続人 | 負担付きの所有権 |
配偶者居住権は完全なる所有権ではないため、建物の売買や賃貸を自由に行うことはできません。
これまで配偶者が被相続人名義の自宅に住み続けるために自宅を相続すると、相続分の関係で他の現預金などの財産を相続することができず、生活に困窮してしまうケースがありました。
相続人同士の関係性が良好であれば、他の相続人が自宅を相続したうえで配偶者が住み続けることも可能ですが、認知した子供や養子、兄弟姉妹などが相続人になる場合には、話し合いがうまくいかず、配偶者が住み慣れた自宅を追い出されたり、生活費を相続できなくなったりするリスクがあるのです。
改正法では、遺言書や遺産分割協議書において別途配偶者居住権を記載することで、所有権と切り離せるようになったので、自宅に住み続けるという権利を取得しても、一定の現預金資産を相続できるようになりました!。
また、相続開始後6ヶ月経過の日までについては、配偶者が自宅を無償で使用できる「配偶者短期居住権」が規定され、特段の取り決めがなくても、配偶者が相続と同時に自宅を追い出されることがなくなります。
自筆証書遺言に関するルールを緩和
これまで自筆証書遺言については、その公正さを守るために作成における細かな規定が設けられていました。
しかし、時代の変化に合わせて、作成方法や保管方法の要件がより緩和され、次のような事項が認められるようになったのです。
財産目録をパソコンで作成してもOK
自筆証書遺言は、添付書類も含め本人による直筆で書くことになっていました。
しかし、あらゆる財産を全て直筆で記載することは大きな負担だったといえます。
今回の改正では、現代では一般的な方法となっているコピーやパソコン利用による財産目録の作成も認められるようになりました。
自筆証書遺言を法務局で保管できる
自宅保管が主である自筆証書遺言は、紛失や偽造等のリスクが常につきまといます。
こういったトラブルを避けるためにも、法整備によって自筆証書遺言をさらに活用しやすい環境を作りました。
事前に手続きをすることで、遺言書の原本と画像データを法務局で保管してもらえるようになったのです。
自筆証書遺言の保管手続きは、以下の住所地を管轄する法務局で行います。
- 遺言書を作成した人の住所地を管轄する法務局
- 遺言書を作成した人の本籍地を管轄する法務局
- 遺言書を作成した人が所有している不動産の所在地を管轄する法務局
相続開始後については、全国どこの法務局からでも自筆証書遺言の画像データを閲覧できるようになりました。
当事務所としてもご依頼者様が制度を上手に活用できるようサポートしていきます。
自筆証書遺言の作成時点から弁護士と二人三脚で対応していくことで、法務局での保管手続きについてもスムーズに行うことが可能です。
遺言書を作成する方の意思を正しく把握し、望んでおられることをしっかりと反映させられるよう、経験豊富な弁護士が親身になって対応いたします。
また、当事務所の弁護士は税理士登録も行っていますので、税務面でのサポートも安心してお任せください。
相続権を持たない親族に対し故人に寄与した分が評価される
故人に対し献身的に介護等を行ったが相続権を持たない親族がいる場合、従来の仕組みでは財産を相続することは叶いませんでした。
しかし、寄与した分が評価されないことは不公平であるとして、このようなケースにおいては、相続権を持たない親族であっても「特別寄与料」として請求できるようになったのです。
特別寄与料が請求できる「特別寄与者」については、法定相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)で、被相続人の子の配偶者などがこれに該当します。
これにより、長年にわたって義理の両親の療養看護を行ってきた人にも、一定の財産を取得できる可能性が出てきました。
法改正に関連するご相談は、当事務所までお気軽にどうぞ
相続は決め事や法律等が複雑に絡み合う問題であるため、よくわからないままでは損をしてしまう可能性が出てきます。
遺産として何がどの程度まで認められるのか、自分が主張できる権利にはどのようなものがあるのか、知らないことによるリスクと隣り合わせであることをご理解いただければ幸いです。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様とのコミュニケーションを重要視しております。
法改正による疑問や不安、そしてご希望されること等を丁寧にヒアリングしていきますので、まずはご相談いただければ幸いです。

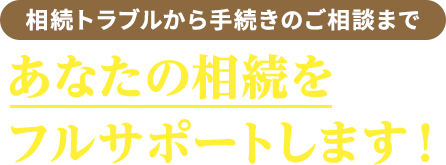
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。