相続財産は「法定相続分」に従って分割することが一般的です。
しかし、実際には、献身的に介護を行ってきた法定相続人の子もいれば遠く離れて親の世話をすることができなかった子もいるでしょう。
このように、被相続人の生活上、特別に貢献してきた法定相続人に対しては「寄与分」という形で法定相続分の上乗せが認められることがあります。
ここでは、寄与分を請求できる例とその計算方法について解説します。
寄与に該当する様々な例
生前の被相続人に対し特に献身的に尽くした相続人には、貢献度を金銭換価し「寄与分」として受けることができます。
寄与分はどのようなケースでも主張できるわけではなく、自己犠牲を払っても被相続人のために貢献したかどうかが1つの基準です。
| 生活支援 | 被相続人を扶養に入れたり生活費の支援をしたりした |
|---|---|
| 看護あるいは介護支援 | 被相続人の看病や介護を献身的に尽くした |
| 債務支援 | 被相続人の借金を代わりに負った |
| 事業支援 | 被相続人が営む事業について専ら無償で業務を手伝った |
上記のように、貢献を金銭換価するのが寄与分ですが、実際には相続人による遺産分割協議を通して貢献度を計り金額を決定します。
しかし、他の相続人にとっては、寄与分を多く認めることで自分の取り分が減ることになるので、話し合いでは解決に至らないこともあります。
話し合いでまとまらない場合は、裁判所に調停を申し立て、調停委員を通して互いの主張をすり合わせていく必要が出てくるでしょう。
寄与分が認められる場合の計算方法
上述のような寄与が認められた場合、相続財産は以下の計算方法で算出します。
- 遺産総額から寄与分相当額を引いて「みなし相続財産」を算出する。
- みなし相続財産に法定相続割合をかけて各法定相続人の相続分を算出する。
- 寄与した相続人は相続分に寄与分を足した分を相続する。
例を挙げて考えてみましょう。
遺産が1,000万円で、法定相続人が配偶者と子2人(AとB)だった場合、通常であれば子Aと子Bは250万円ずつ相続することになります。
しかし、子Aは被相続人の看病から介護に至るまで献身的に尽くしてきたので、法定相続人はその点を考慮して寄与分を200万円とすることにしました。
この時の寄与分計算例は次のようになります。
- 遺産総額1,000万円から寄与分200万円を引く=800万円(みなし相続財産)。
- みなし相続財産の800万円を法定相続割合に応じて分け合う。
- 寄与した子Aは法定相続分の200万に加え寄与分の200万円をさらに受け取ることができる。
結果として、配偶者の相続分は400万円、子Bの相続分は200万円、子Aの相続分は400万円となり、寄与分が反映されたことになるのです。
寄与分を認めてもらうために当事務所の弁護士がお力になります。
当事務所の弁護士が寄与分についてご依頼を受けた場合、日記や預貯金等の証拠から寄与したことを主張し、証拠がない場合は、他相続人と十分に交渉して事情をわかってもらい、寄与分を認めてもらえるよう尽力しています。
事業面で貢献してきたのであれば、ご依頼者様から「何年間働いて、どのように売り上げを上げたのか」を詳細にヒアリングし、証拠となり得るものを探すこともあります。
寄与分が認められれば、他の相続人が受け取れる財産は減ることになるため、相続人同士の争いに発展することも少なくありません。
相続人が争うような展開を避けるためにも、被相続人は生前に遺言書を用意しておくことがとても大切です。
トラブルを避けるためにも遺言を遺しておくべき
自分が被相続人となった時に相続させる財産がある場合は、予め遺言書を用意し、後のトラブルを回避できるようにしておきましょう。
特に、自分のために尽くしてくれた相続人に寄与分として多く財産を譲りたい場合は、遺言書の果たす役割が大変重要になってきます。
遺言書の作成においては、専門知識と経験を有する当事務所にぜひご相談ください。
弁護士がいれば有効な遺言書を作成し保管しておくことができます。
特に当事務所の弁護士は税務面でのサポートも可能ですので、安心してお任せください。
どのような気持ちから遺言書を残したいのか、相続開始後にどのような展開になることを望んでいるのか、しっかりとお話を伺った上でベストなサポートを心掛けています。
遺言書がない場合の寄与分
遺言書が残されていない相続において、寄与分を認めてほしい方については、ご自身で直接交渉しても他の相続人の理解が得られない可能性が高いので、まずは一度当事務所にご相談いただくことをおすすめします。
寄与分や特別受益といった、法定相続分よりも多い相続分を望む場合、訴訟になると認めてもらうことが非常に難しいため、基本的にはそれらも踏まえて交渉の中で落とし込むことが重要です。
当事務所にお任せいただければ、ご依頼者様の代理人となって他の相続人に事情を丁寧に説明して穏便に理解してもらえるよう粘り強く交渉いたします。
寄与分や特別受益を望まれる方は、できる限りお早めに当事務所までご相談ください。

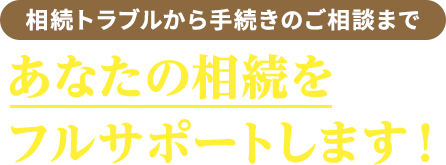
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。