相続は一生のうち数えるほどしか経験しないことですから、手続きの手順・スケジュールの全体像を把握している方は少ないのではないでしょうか。
相続手続きの中には期限が定められているものもありますから、全体のスケジュール感については、おおよそでいいので、事前に理解しておきましょう。
ここでは、相続手続きの流れとスケジュール(期限)についてお伝えします。
相続関連手続きを時系列で整理する
相続手続きのゴールは「相続税の納税」にありますが、そこに至るまでには様々な作業や手続きが存在します。
まずは、わかりやすく時系列で整理していきましょう。
3ヶ月以内:相続するか放棄するかを決める
相続人は、被相続人の財産を「相続する」か「放棄する」か選ぶことができますが、それを判断するためには次の2つの調査を実施する必要があります。
| 相続人調査 | 家族や親族の中で誰が相続人であるかを知るために戸籍謄本から家系図を作成すると、比較的容易に把握することができるでしょう。相続人調査はどのような場合においても戸籍を利用するやり方が一般的です。 |
|---|---|
| 財産調査 | 預金通帳や郵便物等からどのような財産があるかを把握していきます。財産の中で大きな比重を占めるのは、主に預貯金と不動産、有価証券です。財産調査が終わったら、財産の一覧を記した「財産目録」を作成しましょう。 |
以上について整理できたら、今度は財産を相続するのかどうかを決めましょう。
取り分全てを受け継ぐ「単純承認」、受け継いだプラスの財産の範囲内でのみマイナス財産を受け継ぐ「限定承認」、あるいはすべての権利を手放す「相続放棄」の中から選択します。
限定承認や相続放棄を選択する場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述し、それを受理してもらわなければなりません。
3ヶ月の期限を過ぎると、原則的に単純承認したこととみなされてしまいます。
大変短いスケジュールとなりますので、特に限定承認、相続放棄をご検討の方は期限を意識して手続きを進めるようにしましょう。
4ヶ月以内:被相続人の所得税について準確定申告を行う
自営業者は翌年3月15日までに確定申告を行わなければなりませんが、被相続人が事業を営んでいた場合(所得税の申告義務を負っていた場合)等も、これに準ずる「準確定申告」が必要となります。
準確定申告の期限は相続開始から4ヶ月以内です。
お亡くなりになった時点での所得額が申告対象であれば「準確定申告」を行う必要があるので、それまでに準備を進めておきましょう。
10ヶ月以内:相続税納付
被相続人が遺した財産が課税対象となった場合、相続開始日の翌日から起算し10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行います。
全ての相続人が実際に相続した財産に対して課税されますので、期限内に相続人の確定や遺産分割協議、相続方法の決定等の各種作業を済ませておかなければなりません。
その上で、相続人全員で税の申告と納税を行うこととなります。
損を回避するためには当事務所まで早めのご相談を
実際に相続を経験してみるとわかるかと思いますが、10ヶ月は非常に短く感じるはずです。
さらに慣れない手続きでもあるでしょうから、不備も発生しやすくなります。
遺産の範囲を的確に把握したり、自分の権利を適切に行使するためにも、わからないことがあれば積極的に専門家に相談してみましょう。
当事務所では、相続問題に関して常に感情面での配慮を欠かさず、精神面のフォローを行うことによって円滑な解決を目指しています。
親族同士で相続に関する話をした場合、揉め事を避けたい気持ちからいうべきことを抑えてしまうこともありますし、そのまま時間が経過すれば主張できる権利も獲得しにくくなっていくからです。
例えば、以下のようなケースでは当事務所の弁護士によって内容をまず明らかにすることが必要です。
- 遺産の内容や範囲が曖昧である。
- 被相続人と相続人の生前の関係性が希薄だった。
- 寄与分や特別受益を主張できる可能性がある。
こういった状況においては、弁護士の専門的な知識を持って対応することで、自分自身の権利を守り、適切な遺産分割を実現することが可能になります。
「知らない」ことで被る不利益を避け、適切な相続分を取得するためにも、できる限りお早めにご相談ください。

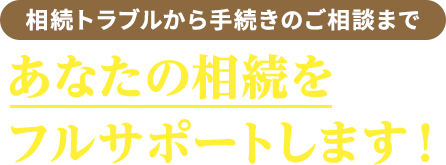
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。