遺言が残されていない場合、誰がどれぐらい相続するかは「遺産分割協議」によって決めることになります。
その前に、誰が相続人なのか、そしてどれぐらいの遺産があるかを調べることは相続を行う上でとても重要な手続きです。これらに漏れがあったり、抜けがあると最悪遺産分割協議のやり直しになってしまうかもしれません。
今回は、法定相続人の範囲と遺産分割協議の進め方について解説します。
誰が法定相続人になるのか
遺産分割協議を行う前に「だれが相続人であるのか」を確定させなければなりません。遺言書がなければ、民法の定めに基づいて「法定相続人」が相続人となります。
法定相続人となるのは以下の方々です。
配偶者
配偶者は常に法定相続人となります。ただし、婚姻関係にある配偶者が対象であるため、内縁の妻や離婚した夫等は含まれません。相続分は1/2となります。
子
配偶者に次いで優先される存在が、被相続人の子です。相続における第1順位とされており、配偶者の取り分を除いた残り1/2を子の人数で分けることになります。子が先に亡くなっていた場合は、さらにその子(被相続人の孫)が代襲相続によって法定相続人となります。
直系尊属(親、祖父母)
子がいなかった場合、第2順位として優先されるのが被相続人の直系尊属になります。両親ともにすでに亡くなっていた場合は、被相続人の祖父母が法定相続人です。相続分は配偶者2/3に対し、直系尊属で残る1/3を分配します。
兄弟姉妹
子も親もいない場合の法定相続人は、第3順位にある被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合は、その子(被相続人の甥姪)が相続します。相続分は、配偶者3/4に対し兄弟姉妹で残る1/4を分けることになります。
被相続人が残した財産の内容を明らかにする
相続人が誰か明確になったら、次に個人の財産内容を確認し整理していく必要があります。遺産の範囲には、金銭的価値のあるプラスの財産に加え、借金等を含むマイナスの財産も含まれます。漏れのないように財産目録を作成しましょう。
プラスの財産に該当するもの
現金、預貯金、土地や建物等の不動産、自動車等の動産、株券、著作権等
マイナスの財産に該当するもの
借金、未完済のローン、連帯保証人義務、未払い税金等
相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人と相続財産、いずれも明確になった時点で「遺産分割協議」を開始しましょう。遺言書がなければ、法定相続分がそれぞれの相続分の目安となります。
遺産分割協議と聞くと、一か所に全員が集結して話し合いをするイメージがあるかもしれませんが、実際は相続人が遠方に住んでいたり、仕事で忙しかったりすることが多いため、紙やメールなどで話し合いを進めていくことが多いです。
話し合いが順調に進み、全ての相続人が分割内容に納得したら「遺産分割協議書」を作成して全員が署名捺印します。
遺産分割協議のポイント
相続分は法定相続分が基本となりますが、次のような事情がある場合は法定相続分とは別に考慮される可能性があります。
特別受益について
被相続人から特別な支援(特別受益)を受けていた場合、その分を考慮した取り分を主張することが可能です。具体的には、特別受益分も相続財産に持ち戻したうえで遺産分割を行うことで調整します。
寄与分について
介護や事業に対する献身など、ある相続人が被相続人に対し特別な貢献を行っていた場合、寄与分として、法定相続分よりも多く財産を取得できる場合があります。
遺産分割協議は弁護士に依頼するとスムーズに解決しやすい
遺産分割協議は当事者のみでも行うことはできますが、弁護士をはじめとした専門家に依頼された方がよりスムーズかつ、ご希望に沿う形での解決を実現できます。
当事務所では、遺産相続のサポートにあたり次の点に特に気を配っております。
- 今までの経緯を丁寧にお伺いし、ご依頼者様にとって適切な解決を提示する。
- 相続人同士の争いごとができる限り起きないよう、慎重に話し合いを進める。
相続問題は、法的な解釈のみでうまくいくとは限らず、「公式にあてはめて終わり」というシンプルな世界ではありません。
ご依頼者様それぞれの思いを汲み、どうすればより満足と納得を感じられる結論に至ることができるかを、常に追求しています。
実務面としては、相続人の範囲はもちろん、遺産の対象となるものの把握や主張すべき権利等、知らないと損に繋がってしまうケースをいかにして防ぐかについて配慮しております。
法的なことを知らないために不利益を被らないよう十分に配慮し、適切な配分を得られるよう取り組みます。
親族間のことであるからこそ、ちょっとしたことで相続トラブルに発展する可能性は決して低くありません。そうなった場合は、早めに弁護士に依頼し、冷静かつ正確で公平な視点で解決していくことが求められます。
初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

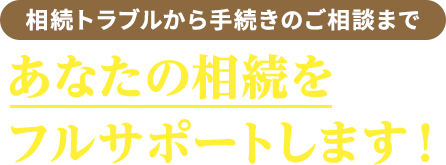
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。