遺言者が所有する財産について、相続開始後にどう配分して欲しいかを記すのが遺言書の役割です。
しかし、法律に定められた形式に基づかないで作成された遺言書は無効とされてしまいます。
ここでは、遺言書の種類による無効例を紹介し、無効とされないための対策について解説します。
無効例(1)自筆証書遺言
自分1人で自由に作成できる自筆証書遺言は人気が高いといわれていますが、遺言書としての原則に則っていなければ無効とされてしまいます。
直筆で作成されていない自筆証書遺言
遺言者の直筆によって作成するのが自筆証書遺言ですから、パソコンで作成したものや肉声を録音あるいは録画したものは有効とされません。
ただし財産目録等については、2019年1月13日の法改正により、一覧表をパソコンで作成したり通帳のコピーを提出したりすることが認められました。
正式な日付や署名捺印がない自筆証書遺言
遺言書に記載する日付は、何年何月何日と正確でなければなりません。
従って、以下のような記載は遺言書無効の原因となってしまいます。
- 令和元年六月吉日
- 令和元年六月末日
これらの日付記載では、具体的な日付がわかりませんので注意しましょう。
また、自筆署名や捺印のない遺言書も無効となります。
自筆証書遺言は法律で形式が定められていますから、漏れなく正しく作成するよう気を遣わなければなりません。
自筆証書遺言の作成方法は書籍やネットで調べることができるため、多くの方が参考にしていることでしょう。
しかし、当事務所では、非常に大切なことだからこそ弁護士に依頼すべきだと考えています。
- ネット情報が正しいとは限らないが弁護士なら正誤の判断がつく
- 法的根拠に基づき、かつ自分の意思を反映できたという満足感や結果に結びつく
- 間違った情報で遺言書を作成し、経済的損失や相続人同士の状況悪化に結びつくことがない
安易にネットの情報を鵜呑みにし、後に問題が複雑化するよりは、最初から当事務所の弁護士に依頼した方が良いでしょう。
無効例(2)公正証書遺言
法律の専門家である公証人に対して遺言内容を口述し、確認を受けた上で保管もしてもらえるのが公正証書遺言の特徴です。
その法的信頼性から家庭裁判所による検認も免除されていますから、公正証書遺言が無効とされる可能性は極めて低いといえるでしょう。
ただし、過去に公正証書遺言でも作成時の本人の遺言能力などをめぐって争いが起きた事例がありますので、100%確実とまでは言い切れません。
無効例(3)秘密証書遺言
遺言内容を誰にも知られることなく、遺言書が確かに存在することを公証人に証明してもらえるのが秘密証書遺言です。
秘密証書遺言は公証人が存在を証明することから、遺言書の全文をパソコンで作成することも可能です。
ただし、秘密証書遺言の要件として、以下のことが満たされていない場合は無効とされる可能性が出てきます。
- 遺言書の封筒に日付が記載されていない。
- 遺言書に遺言者の署名捺印がない。
- 封筒に遺言書と同じ署名捺印がされていない。
以上を満たしていることは原則的条件ですので、無効とならないよう確認を徹底しましょう。
また、秘密証書遺言は公証人役場で保管されませんので、紛失しないよう自ら厳重な管理が必要になります。
相続開始と同時に遺言書を検認に出してもらえるよう、保管場所や委任者を決めておくことも大切です。
有効な遺言書を作成するためにも当事務所の弁護士まで早期相談を
有効な遺言書を作成するためには、まだ元気なうちから当事務所へのご相談・ご依頼をおすすめしております。
弁護士がいれば法的に無効とならない遺言書を予め用意しておけるからです。
また、当事務所の弁護士とご依頼者様との密なやり取りを通して、相続開始後に誰もが納得できる遺言内容を作り上げていくことも可能です。
特に、自分1人で作成できる自筆証書遺言や秘密証書遺言は、作成ミスが原因となり相続開始後の問題となることもありますので、早めに弁護士相談をすれば間違いがありません。
ご依頼者様の相続開始時には、弁護士という法律の専門家がサポートすることにより、迷いのない手続きを遂行することができるでしょう。
遺言執行者として受任していれば相続人の方々を煩わせることもありません。
せっかく作成した遺言書が有効とされるためにも、また相続開始後のスムーズな手続きを可能にするためにも、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

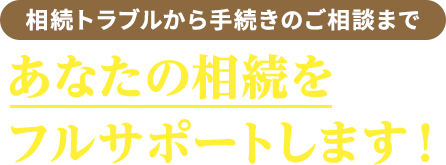
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。