相続は必ずしもスムーズに行われるとは限らず、相続人同士の利害や感情が衝突することもあります。
話し合いだけでまとまらない場合は、調停や裁判を利用しなければなりません。
このような自体を避けるためには、被相続人が予め遺言書を作成しておくことが有効だと考えられます。
ここでは、遺言書の種類と弁護士に作成を依頼すべき重要な理由について解説します。
弁護士に遺言書作成を依頼するメリット
遺言書には大きく3種類あり、中には自分1人で作成・保管できる方法も存在します。
しかし、様々な法律が絡む相続について正しく遺言書を作成することは困難ですし、相続開始後の相続人同士の争いに関する心配も出てくるでしょう。
その点、当事務所の弁護士に遺言書作成を依頼すれば、次のような安心を得ることができます。
- 法的根拠に基づく正しい遺言書作成が可能になる。
- 予想されるトラブルへの対策をとることができる。
- 税理士登録もしている弁護士であるため、税務面でのアドバイスも受けられる。
3つの遺言書の特徴を知っておこう
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれに特徴を持っています。
自筆証書遺言
遺言書原本及び財産目録等の一連の書類を全て自筆で作成する遺言書が自筆証書遺言です。
紙とペンがあれば誰でも自分で遺言書を作成できるので、とても人気が高い方法だと言えます。
従来の法律では、財産目録等の付帯書類も全て自筆で作成することになっており、作成者の大きな負担になっていました。
その点が見直され、2019年1月13日から財産目録をパソコンで作成することが可能になりました。
また、遺言書の保管方法についても改正され、これまで自己責任による保管が必要だったところ、今後は自筆証書遺言でも公証役場での保管が可能になります。
公正証書遺言
公証役場で遺言書を作成する方法を公正証書遺言といいます。
作成方法は以下の通りです。
- 遺言内容を公証人に口頭で伝える。
- 公証人がそれを書き取る。
- 公証人、遺言者、立会人全ての関係者が署名捺印する。
- 作成した遺言書の原本は公証役場で保管される。
以上の手順を踏むことから、とても正確性と安全性が高い方法とされています。
法律を専門分野とする公証人(元裁判官など)のもとで作成する遺言書ですから、内容に間違いが起こることがなく、不正のリスクを避けることができ、家庭裁判所による検認を受けることもありません。
秘密証書遺言
遺言者が独自に遺言書を作成して公証役場に持ち込む方式を秘密証書遺言といいます。
遺言書の内容は誰にも知られることがなく、証人2人を伴い公証人のもとで遺言書と同じ捺印と署名を行うので、間違いなく本人のものであることが証明されるのです。
ただし、遺言内容は公証人・証人ともに確認することができないので、内容の法的な不備や相続時のトラブル回避等のリスクを伴うといえるでしょう。
また、相続開始時には、家庭裁判所による検認を受けなければ遺言書を開封することができません。
納得できる遺言書を作成するなら当事務所の弁護士にご依頼を
遺言書は、遺言者本人の思いを遺産分割という形で家族や親族に伝える行為でもあります。
しかし、相続自体が相続人同士のトラブルになりやすいことも事実でしょう。
だからこそ、遺言者本人だけでなく残された相続人にとっても納得できる遺言書を作成することがとても大事なのです。
遺言書作成における当事務所のサポートの特徴
相続は財産分割の話し合いであるため、家族や親族同士だと言いづらいこともでてくるでしょう。
揉めたくないという思いから互いに気を遣い合った結果、話がなかなか進まないこともあるのです。
このような現実を踏まえ、当事務所では相続人同士が気持ち良く円滑に手続きを進められるよう、精神面でのケアも欠かしません。
誰がどのように考えているか、言いづらいことは何なのか、どのような点が解決すればよりスムーズに進むのかまで、特に感情面に配慮しながらサポートしています。
弁護士という法律の専門家がいるだけで、相続人の方々にとっては、遺産分割協議の疑問や不安を解決しやすいですし、とても冷静に話し合いに参加することができるでしょう。
万が一揉め事が発生してしまったとしても、現状より問題が悪化しないよう、弁護士が納得できる解決策を示していきます。
遺言書作成のサポートで当事務所が最も心掛けていることは、遺言者が望む内容は何なのかを把握し、その思いを遺言書に反映させる点にあります。
そのためにご依頼後のコミュニケーションに重点を置いておりますので、ぜひ安心して当事務所までご相談ください。

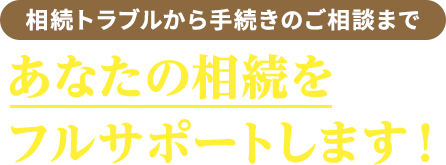
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。