法定相続分は、相続財産の分割方法の1つの指標として扱われており、対象者とその取り分を示しています。
実際の相続においても、法定相続分に従って相続人の相続分を決めるのが一般的です。
今回は、遺産相続における法定相続分に関する基本的な知識について解説します。
民法で定められた「法定相続人」とは
被相続人の財産を相続できる者は、民法で「法定相続人」として定められています。
どのような人が法定相続人になるのか、以下に整理していきましょう。
配偶者:常に法定相続人
被相続人の夫または妻は常に法定相続人となります。
被相続人の子供:相続第1順位
被相続人の子供は、相続における第1順位として扱われます。
子供には実子だけでなく養子や認知された子を含みます。
仮に子が先に亡くなっていた場合は、その子(被相続人の孫)が相続人としての立場を得ます(代襲相続といいます)。
被相続人の直系尊属:相続第2順位
被相続人に子や孫がいない時は、第2順位として直系尊属である親が相続権を持ちます。
親が先に亡くなっていた場合はその親(被相続人の祖父母)が相続人としての立場を得ます。
被相続人の兄弟姉妹:相続第3順位
被相続人に子や直系尊属がいない時は、兄弟姉妹が相続権を持ちます。
兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合はその子(甥姪)が相続人としての立場を得ます。
遺言により遺産を取得する人を指定できる
前述の通り、法律では法定相続人となる者を定めていますが、内縁の妻や孫といった「相続権を持たない人」に財産を譲りたいケースも考えられます。
このような場合は、予め遺言書を作成しておくことによって、相続人以外の人に対しても財産を譲る相手に指定することが可能です。
当事務所では遺言書の作成依頼もお受けしており、次のようなことに気をつけて作成のサポートをしています。
- ご本人が誰にどの財産をどれくらい譲りたいのか、ご希望を理解把握する
- 税理士登録を活かし税務面での助言を行う
- 有効な遺言書となるよう細部まで確認し助言を行う等
特に、遺言書作成に至った「お気持ち」の部分は最重要視すべき点ですので、しっかりとコミュニケーションをとって満足のいく遺言書の完成を目指しています。
遺言書作成時は「遺留分の侵害」に注意する
遺言書で指定した相続分については、法定相続分よりも優先されますが、遺留分まで侵害してしまうと相続トラブルの原因となります。
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、法的に保護されている相続分のことです。
遺留分の割合
| 配偶者、子のみ | 1/2 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 1/2 |
| 直系尊属 | 1/3 |
上記割合を超えた分に関しては、「遺留分侵害額請求」をされると返還しなければなりません。
その点をご依頼者様に丁寧にお伝えしたうえで、遺言書に記載する内容をご提案していきます。
公平かつスムーズな相続を実現するには弁護士が必要
遺産分割協議で揉めてしまっているような場合は、当人同士での話し合いでは解決しないケースが多々あります。
そのような場合はできるだけ弁護士に相談の上、相続手続きを進めることをおすすめしています。
話し合いで解決できない場合は調停等の法的手続きが必要となりますが、有利に進めるには行う主張を戦略的に考えなければならないことに加え、書類の準備もしなければならず、弁護士の力を借りずに乗り切ることはなかなか困難と言えます。
経済的な利益はもちろんのこと、慣れない手続きをすべて代わりに行ってくれることで得られる精神的なメリットも大きなものと言えるでしょう。
トラブルのない相続を実現するためにも当事務所までご相談ください
相続で一番問題になりやすいのが、相続人間の軋轢だといえます。
親族同士だからこそ、それぞれの思い入れや希望がぶつかり合うことになりやすいからです。
弁護士としては、ご依頼者様に対して適切な解決策をご提示したいと考えております。
法的な回答を示すことは当然ですが、人間関係がベースとなる相続問題を気持ちよく解決するためには、やはり金銭的・先進的なフォローが欠かせません。
法的解釈だけではなく、ご依頼者とじっくりコミュニケーションをとる中で思いを十分に汲み取り、オーダーメイドのベストな解決策をご提案いたします。
不安をなくしより納得のいく相続を実現するためにも、できる限りお早めに当事務所までご相談いただければ幸いです。

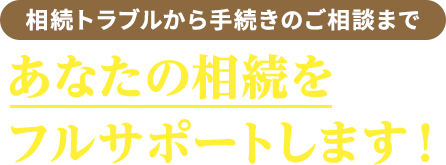
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。