被相続人に前妻の子や非嫡出子がいた場合、その子らは相続人として財産を相続できるのでしょうか。
また、前妻の子や非嫡出子に財産を取得させるためには、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは、前妻の子や非嫡出子がいる方がとるべき、有効な相続対策ついて解説していきたいと思います。
非嫡出子の相続について
相続権があるかどうかは認知の有無によって変わる
非嫡出子とは結婚していない男女の間に生まれた子供のことで、相続権の有無については、父親が子を認知しているかどうかで決まります。
父親となる男性が子を「自分の子である」と認知した場合、その子は法定相続人としての権利を有することになるため、他の相続人と同じように遺産分割協議に参加することが可能です。
一方、男性が子を認知していなかった場合、その子は法律上の「子」とならないため、相続権を持たないことになります。
非嫡出子の相続割合
かつて非嫡出子の取り分は嫡出子の1/2と定められていました。
しかし、同じ親から生まれたにも関わらず公平ではないなどの理由から、平成25年の最高裁判決によって非嫡出子・嫡出子ともに同じ相続分が認められることとなった経緯があります。
非嫡出子に遺産を取得させる方法
非嫡出子にも財産を残したい場合、まずは「認知」することです。
認知をすれば、相続における法的な地位は、他の子と同じになります。
生前に認知することが難しい場合は、遺言書によって認知をすることもできますが、その際には本人に代わって認知の手続きをする遺言執行者も指定しなければなりません。
弁護士は遺言執行者として遺言認知のサポートを行えます。
ご希望の方はお気軽に当事務所までご相談ください。
前妻との子の相続について
前妻との子は正当な法定相続人である
離婚経験を持つ被相続人は、前の妻または夫との間に子がいる場合があります。
たとえ離婚していたとしても、婚姻関係による子のため嫡出子となり、正当な法定相続人として認められることを覚えておきましょう。
前妻の子の遺留分について
遺言書であまりにも偏った相続分を指定した場合、不利益を被った法定相続人は「遺留分」を主張して遺留分の返還(遺留分侵害額請求)を求めることができます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている保護された相続分のことで、前妻の子にも認められています。
仮に「すべての財産を後妻の子であるAに相続させる」といった内容の遺言書が見つかった場合でも、前妻の子は民法の規定に基づき遺留分の返還を求めることが可能です。
実際に遺留分を請求する行為を「遺留分侵害額請求」といいますが、できるだけ弁護士に依頼した上で手続きを進めるほうが望ましいです。
遺産の範囲や評価に不備があると請求者が不利益を被ることがある上、請求権は相続開始を知った時点から1年で時効消滅してしまいます。
もっとも、請求する時点でトラブルになってしまっているケースがほとんどでしょうから、速やかに弁護士に相談すべき典型的なケースでもあります。
相続発生後のトラブルを防ぐためにも遺言書による対策を
認知していない子や前妻との間に子がいる方は、自身の相続において子供同士が遺産をめぐって争う可能性が考えられます。
認知していない子にも遺産を相続させたい場合は、生前に認知をするか、遺言書によって認知しなければなりません。
し遺言書で認知をお考えなのであれば、これも専門家のサポートを受ける必要性は高いと言えるでしょう。
遺言書には形式(ルール)が定められており、形式を満たしていない遺言は無効となる恐れがあります。
ご自身の意思を確実に実現するためにも、専門家の力を借りながら遺言書作成にとりかかったほうが安心です。
ご依頼者様のお気持ちを遺言書に反映させます
遺言書を作成する際には、ご依頼者様とのコミュニケーションが不可欠と考えております。
相続や遺言書の問題には法律が複雑に絡みますが、ご依頼者様に法的な回答を提示するだけで問題が解決するわけではありません。
公式にあてはめれば終わりではないのです。
人と人との関係を表す相続や遺言書というテーマゆえに、当事務所では、ご依頼者様のお気持ちや状況を十分理解した上で、最適な解決策を共に見つけ出すことを最優先に考えております。
当事務所までご相談にお越しいただく際には、故人が亡くなるまでの経緯や生活状況、家族親族との関係性や財産情報等についてぜひ教えてください。
メモ程度の情報であっても、ご相談時間をより濃密でよいものにするには欠かせない材料となります。
夜間や土日も受け付けており初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご一報いただけますと幸いです。

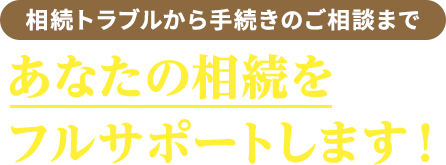
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。