遺言書が発見された場合、公正証書遺言を除く自筆証書遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所で確認作業を受けることになります。
これが「検認」という手続きで、遺言書を開封する前に必ず行わなければなりません。
ここでは、遺言書の検認手続きの概要と流れを解説し、弁護士に遺言書の作成を依頼する大切さについて解説します。
検認手続きとは
遺言書の検認とは、裁判所において相続人立ち会いのもと遺言書を開封して内容を確認する手続きの事です。
そうすることで、遺言書の存在を全ての相続人に対して明確にするとともに、偽造などを防ぐという目的があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、開封前に検認が必須となっています。
先に開封してしまうと場合によっては、5万円以下の過料になる可能性もありますので注意が必要です。
無事に検認手続きを終えると、ようやく被相続人名義の預貯金を解約したり被相続人名義の不動産を登記変更したりといった遺言執行ができるようになります。
なお、検認はあくまで遺言書の形式を確認するだけで、遺言書の有効無効について証明するものではありません。
家庭裁判所における検認手続きの流れ
検認手続きには決まった流れがあり、家庭裁判所に申し立てを行って検認を受けることになります。
それぞれの過程について順を追って整理していきましょう。
提出書類の用意と裁判所への提出
検認の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
遺言書を発見した人か、弁護士等の遺言執行者が申立人となるので、誰が該当するか予め確認しておくようにしましょう。
申し立てには費用を支払う必要があり、遺言書1通につき800円分の収入印紙と返信用切手代を納めなければなりません。
書類を提出してからおよそ1ヶ月から1ヶ月半後に、相続人全員に対して家庭裁判所から検認期日の通知が発送されます。
検認当日には相続人が家庭裁判所に集まって検認手続きを受けることになるため、遺言書と印鑑の持参を忘れないようにしましょう。
検認が終了すると家庭裁判所から検認証明が付くことになります。
これにより相続にまつわる名義変更や預貯金の解約等の手続きを進めることができるようになるのです。
検認申し立てに必要な書類
検認の申し立てには、次の書類を提出する必要があります。
申立書
裁判所又は裁判所ホームページで入手可能。
被相続人の戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本。
相続人の戸籍謄本
全ての相続人の戸籍謄本。
この他、裁判所から別途書類の提出を求められることもあります。
検認手続きは当事務所にお任せください
相続開始後は、大切な家族を失った悲しみから家族や親族は疲弊します。
そのような時に検認手続きで更なる負担をかけないよう、遺言者は遺言作成時から弁護士と相談し間違いのない遺言書の作成を心がけましょう。
当事務所では、弁護士本人がかつて相続問題で弁護士とのコミュニケーションで苦労した経験を持つため、自らは密なコミュニケーションによってご依頼者様との関係性構築に尽力しています。
そのため、生前にご相談いただいた場合、残された相続人が納得できるような遺言書をどう作成すべきか、話し合いを重ねてベストな遺言書作成をサポートすることができるのです。
結果として、遺言者の思いを尊重しつつ将来的なトラブルを回避し検認をスムーズ終えることができるでしょう。
相続開始後でも当事務所は相続人のお力になります。
相続財産の額が大きい場合、相続人から遺言執行者を指定するとその人の負担が非常に大きくなることが考えられます。
また、税務面での難しい問題も出てくるでしょう。
だからこそ、遺言作成時から税理士登録を持つ当事務所の弁護士にご依頼いただき、遺言執行者として事前に指定しておくことがとても大切なのです。
また、相続が開始してからでもご相談は遅くありません。
ぜひ当事務所の弁護士による専門的なサポートを受けていただきたいと思います!。
法律の専門家がサポートすることによって、遺言執行者の負担減はもちろんのこと、相続人の間で起こり得る感情的な問題も回避することができるでしょう。
- 遺産分割協議に当事務所の弁護士が介入すると安心感が生まれる。
- 法的根拠に基づくアドバイスを受けられるので、相続人が不満や疑問を持つことなく遺産分割協議を終えることができる。
- 遺産を握っている相続人との話し合い、調停、訴訟等を段階的に行うことができる。
これら感情的な問題は、家族や親族同士では言いにくいテーマだといえます。
揉め事を避けたい気持ちから時間だけが過ぎていくことは良くありませんので、ぜひ早期のご相談いただければ幸いです。

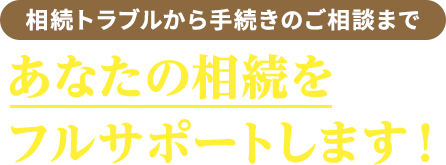
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。