法定相続人が誰もおらず、かつ遺言も残されていない場合については、生前の人間関係等を考慮して、財産の一部を相続人以外の人が受け取れる場合があります。
今回は、相続人以外の人でも遺産を受け取ることができる「特別縁故者」の制度について詳しく解説します。
相続人がいないケースとは
法定相続人のうち、いずれの方もすでに亡くなっている場合や、全員が相続放棄した場合等は、遺産を引き継ぐ相続人がいなくなってしまいます。
相続人がいない場合、被相続人が所有する財産は国庫に帰属することとなりますが、もし「特別縁故者」がいた場合は、財産の一部を取得できる可能性があります。
特別縁故者と認められるための条件
遺言を残すことなく被相続人がお亡くなりになった場合でも、条件を満たす者については特別縁故者として遺産相続を受けることが可能です。
民法には、特別縁故者として認められる条件が明記されており、以下の基準に照らし合わせて判断されます。
被相続人と同居していたかどうか
特別縁故者として申し立てを行う者が、被相続人と同一生計にあったかどうかが1つのポイントです。
内縁関係にあった者や手続きは行っていないが事実上養子として暮らしていた者などが該当します。
被相続人の介護や看護に献身的な取り組みを行ったかどうか
同一生計でなくても、被相続人に対して献身的に看護あるいは介護を行ってきた者も、特別縁故者になれる可能性があります。
ただし、報酬を得て業務として行っていた者は含みません。
被相続人と特別の関係性があったかどうか
親と子のように大変親密な関係があった場合、その者は特別縁故者として認められる可能性があります。
被相続人が深く関与していた法人や団体
一個人でなくても、生前に被相続人が積極的に関わっていた法人や団体も特別縁故者となる可能性があります。
上述のように、特別縁故者として認められるためには、民法の規定に沿っているかどうかが重要な判断基準となります。
ただし、被相続人の状況は人それぞれであり、ケースによって個別に判断されますので、曖昧な一面があることも事実です。
特別縁故者の可能性が考えられる方は、相続を得意とする当事務所までぜひご相談いただき、条件を満たしそうか検証してみることをおすすめします。
相続財産管理人の選任と特別縁故者の申し立て
特別縁故者として基準を満たす可能性がある場合、裁判所に対しどのようにして申し立てるのでしょうか。
ここでは手続きの流れについて解説します。
ステップ1:相続財産管理人選任申し立て
相続人がいない場合は、利害関係人または検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「相続財産管理人」の選任について申し立てをします。
ステップ2:相続財産管理人選任の公告
相続財産管理人が選任されると、官報という国の機関紙に2ヶ月間公示されます。
ステップ3:債権請求申し出の公告
相続人が誰も名乗り出ない場合は、債権者や受遺者に対して、被相続人に対する債権があれば申し出るよう2ヶ月以上公告をします。
ステップ4:相続人捜索の公告
さらに6ヶ月以上の期間を定めて、相続人捜索の公告を行います。
期間が過ぎても相続人が誰も名乗り出なければ、相続人の不存在が確定します。
ステップ5:特別縁故者への財産分与請求
相続人の不存在が確定すると、ようやく特別縁故者へ財産を分与するよう請求することができるようになります。
分与を希望する者は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、3ヶ月以内に請求する必要があります。
ステップ6:財産分与の審判
申し立てを受けた家庭裁判所は内容を審理し審判を下します。
その結果、特別縁故者であると認められた場合、家庭裁判所はどの程度の財産を特別縁故者に分け与えるかも決定を下します。
このように、特別縁故者として財産を受け取るためには、多くのプロセスを経る必要があるのです。
特別縁故者の申し立ては当事務所にご依頼ください。
現代では、インターネットで自ら情報収集して問題解決を図ろうとする流れがありますが、次のようなリスクが潜んでいることを忘れてはいけません。
- インターネット上には間違った情報や古い情報が溢れている。
- 誤った情報をもとに手続きをし、結果として経済的損失を被ったり状況が悪化したりすることもある。
相続はかなり専門性の高い分野ですから、当事務所としては早めに弁護士までご相談いただくことを強くおすすめしています。
特別縁故者についてご相談いただく際には、被相続人が亡くなるまでの経緯がわかるものを、メモ書きでも結構ですのでご持参ください。
特別縁故者として認められるかどうかは、被相続人とご相談者様との関係性がとても重要だからです。
被相続人の財産が国庫に帰する前に、なるべく早く手を打ちましょう。
まずはお早めにご相談ください。

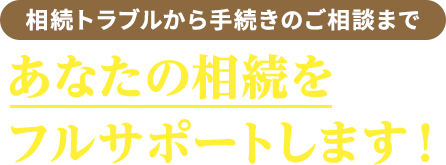
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。