被相続人は、生前に遺言書を準備しておくことによって、誰にどのくらい財産を渡すか指定することができます。
しかし、分配の仕方が著しく不公平である場合、法定相続人は民法で保護されている遺留分を主張することも可能です。
ここでは、遺留分の概要と当事務所の弁護士にご依頼いただくメリットについて解説したいと思います。
遺留分の計算は単純ではありません
法的知識を持たずに遺留分の計算を行うと、正確な算定ができていないことがしばしばあります。
遺産の範囲や評価額など、これらが最終的な算定に関わるからです。
遺留分に関する手続きは専門性が高くなるので、できるだけ弁護士に依頼することが望ましいと考えられます。
遺留分について
遺産相続が発生した際に遺言書があれば、被相続人の望みを反映した遺産分割が可能です。
ただし、著しい不公平まで許容されるかというとそうではありません。
配偶者や子供、親等の直系尊属については、民法で定められている取り分である遺留分(いりゅうぶん)により、最低限取得できる遺産が保護されます。
遺留分の割合
各権利者の遺留分は、民法に定められた遺留分割合にそれぞれの法定相続割合を掛けて求めます。
配偶者・子・親(直系尊属)の総体的な遺留分は、それぞれ次の通りです。
- 配偶者のみ:2分の1
- 子のみ:2分の1
- 直系尊属のみ:3分の1
- 配偶者と子:2分の1
- 配偶者と直系尊属:2分の1
次に、個別の遺留分割合を計算します。
例えば、配偶者と子、配偶者と親(直系尊属)といった組み合わせの場合、上記の割合に法定相続割合を掛けます。
配偶者と子2人
配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
子2人:2分の1×2分の1×2分の1(子の人数分に割る)=1人あたり8分の1
配偶者と親2人
配偶者:2分の1×3分の2=3分の1
親2人:2分の1×3分の1×2分の1(親の人数分に割る)=1人あたり12分の1
遺留分が侵害された場合は遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行う
遺産の使い込みや遺言書などにより、自分の相続分が遺留分に満たなかった場合、多く財産を得た相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
一般的にはまず「遺留分について侵害した分を返還して欲しい」旨を内容証明郵便で相手に送り、任意の話し合いを試みます。
話し合いがうまく進まない場合は裁判所を通して調停や訴訟を行い、解決を目指すことになるでしょう。
ただし、相続問題は親族同士の感情的な軋轢や金銭的な不満がもとになってトラブル化する可能性も否めません。
できるだけスムーズに話を進めるためにもできるだけ早期に弁護士にご相談いただき、正しく対処することをおすすめします。
遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求へ改正
2019年7月から法改正によって、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」に変更となりました。
従来までの遺留分減殺請求については、侵害の対象となっている財産そのものに対してしか返還請求ができなかったため、不動産などが対象となる場合については、現実的に返還に応じてもらうことが難しいケースがありました。
遺留分侵害額請求では、遺留分減殺請求とは反対に金銭のみの返還請求に変わります。
よって、侵害されている対象財産が不動産の場合でも、侵害額を算出して金銭によって支払いを受けることが可能です。
単純な金銭債権化されたことで、これまでよりも遺留分を侵害された際の対処がしやすくなるでしょう。
相続に関するご相談は当事務所にお任せください
当事務所では、ご依頼者様のこれまでの経緯を把握した上で、ご本人にとって最も適切な解決を目指すことを大切にしています。
ご相談内容についても、弁護士として法的な回答は一通り示しますが、公式に当てはめれば解決するわけではありません。
あくまでもご相談者様やご依頼者様のお話を十分参考にして一緒にベストな解決策を探り、できるだけ満足あるいは納得のいく状態に導けるよう尽力しております。
遺留分に関しては、親族同士の問題になるため当事者同士では解決が難しい部分も当然あるでしょう。
遺産の使い込みや著しく不公平な相続分の指定があった場合も、心情的な問題として根が深くなりがちです。
だからこそ、弁護士という専門家に依頼して冷静かつ正しい手続きを進めることがとても大切だといえます。
当事務所では、弁護士本人が税理士でもあり、また司法書士や不動産鑑定士とも連携がありますので、相続手続きのトータルケアとしてご依頼者様の大きな力となることが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

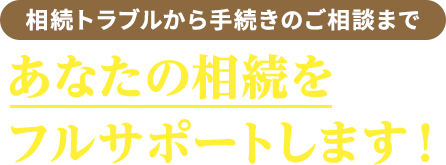
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。