遺言書がなければ、亡くなった方の財産は法定相続人が相続することになります。
遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要がありますが、協議に呼ばれず、結果的に無視された状態が起こることも全くないとは言い切れません。
今回は、そのような場合に行使する相続回復請求権の概要について解説します。
無視された場合は相続回復請求権を主張する
何らかの原因により相続人として無視されてしまった場合、民法第884条を根拠に「相続回復請求権」を主張することができます。
第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
相続人としての権利を回復させ相続分を請求するためには、以下いずれかの期限内に主張しなければなりません。
- 相続人(又は法定代理人)が権利侵害を知ってから5年以内
- 相続の開始から20年経過した場合
上記の期限を超えてしまうと権利が時効消滅してしまうので、早めに対処する必要があります。
真正相続人と表見相続人
法定相続人のように相続権を持つ者のことを「真正相続人」というのに対し、法的権利を持たないにも関わらず相続人と称して財産を得た人のことを「表見相続人」といいます。
表見相続人には次のような者が該当する可能性があります。
- 相続欠格となった者
- 相続廃除された者
- 虚偽の出生届や認知により相続人となった者
- 正しい手続きを踏まず養子同様の立場となった者
真正相続人同士であれば遺産分割協議をやり直すことになりますが、相手が表見相続人の場合は協議自体が成り立ちませんので、相続回復請求権により、本来の相続分を取り戻す必要があります。
相続人以外でも相続回復請求はできる?
法定相続人はもちろんの事、次の者についても相続回復請求によって本来取得できるはずだった遺産を取り戻すことができます。
包括受遺者
遺言書によって包括的に財産の遺贈を受けた人については、相続人と同じように遺産分割協議に参加する権利が認められているため、権利を侵害された場合は相続回復請求によって遺産の返還を求めることができます。
相続分の譲受者
相続を辞退した相続人から相続分の譲渡を受けることがあります。
相続分の譲渡を受けた人も、相続人と同じように相続回復請求をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをするのが面倒な場合や、相続税の問題等で相続放棄をせず相続分を譲渡するケースについては、該当する可能性が出てくるため注意が必要です。
相続財産管理人
相続人がいないケースにおいて、利害関係人や身内などの申し立てによって相続財産管理人が選任されることがあります。
相続財産管理人は、相続人の代わりに相続財産を管理する権限がありますので、遺産を不当に取得された場合は相続回復請求が可能です。
遺言執行者
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要なことを行う権限を有する者のことで、遺言書で指定されているケースがあります。
遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が単独で遺言書の内容に沿って遺産の名義変更手続きなどを行うことが可能です。
勝手に遺産を取得する行為は、遺言執行の妨げとなるため、相続回復請求が可能とされています。
相続回復請求の流れ
まず内容証明郵便を相手方に送付することが一般的です。
相手に連絡を取り話し合いをもって解決を目指します。
すでに相手方が財産を確保している場合等は、話し合い自体が困難になっていることも少なくありません。
そのような場合は、裁判所を利用した調停や訴訟といった手続きによって解決を目指すことになります。
調停、裁判となると作成しなければならない書類や、準備しなければならない証拠資料などが多岐にわたるため、ご自身で対応するには限界があります。
当事務所にお任せいただければ、相続人の方に負担がかからないよう、手続きに必要な書類関係の手配は弁護士が対応し、期日当日についても弁護士が代理人として対応することが可能です。
訴訟においては、次のようなことを主張することになります。
- 自分が法定相続人である
- 財産は被相続人が遺したものであり正当な相続人が相続すべきであること
- 以上を示す十分な証拠の提示
裁判所を通した手続きは非常に専門性が高く、よい結果を得るための知識や経験も求められます。
自力で臨むよりも、相続問題の経験を持つ当事務所の弁護士まですぐにご相談いただくことをおすすめいたします。
相続回復請求権の問題は経験豊富な当事務所にご相談ください
当事務所は、相続に関連するご相談に力を入れております。
弁護士自身がかつて相続を経験しており、実際に弁護士に依頼して問題解決を図り、事業承継に関する複雑な問題に長年苦労したことがあるため、思い入れが非常に強いです。
相続問題は人間関係が密接に絡む
依頼者側と弁護士側の両方を経験して思うのは、相続問題は人間関係問題と密接な関連性を持っているということです。
財産という現実的な損得問題に留まらず、精神的なストレスが大きくなる点や問題の長期化等、本人の健全な生活や親族関係に、よい影響を与えない一面があるといわざるを得ません。
そのため当事務所では、受任時点からご依頼者様に代わって交渉や訴訟手続き等を行っていき、精神的な負担を軽減することを非常に重要視しているのです。
法的な回答は一通りしますが、あくまでもヒアリングに重点を置き、ご依頼者様のご事情や経緯をしっかりと把握することで、問題の争点を明確にし、どのように解決することが最も望ましいのか、しっかりとコミュニケーションを取りながら二人三脚で進めます。
法的な問題は公式に当てはめて終わりという世界ではありませんので、単に法律に基づいた解釈を行えばよいのではなく、ご依頼者様とともにゴールを目指すという意識が欠かせません。
当事務所であれば、弁護士自身が依頼者の立場を経験していることに加え、弁護士としての実務経験も豊富ですので、ぜひ少しでも早く当事務所までご相談いただければ幸いです。

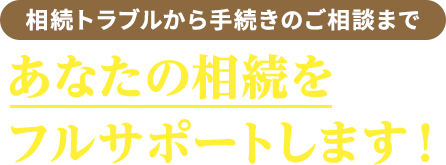
 まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。